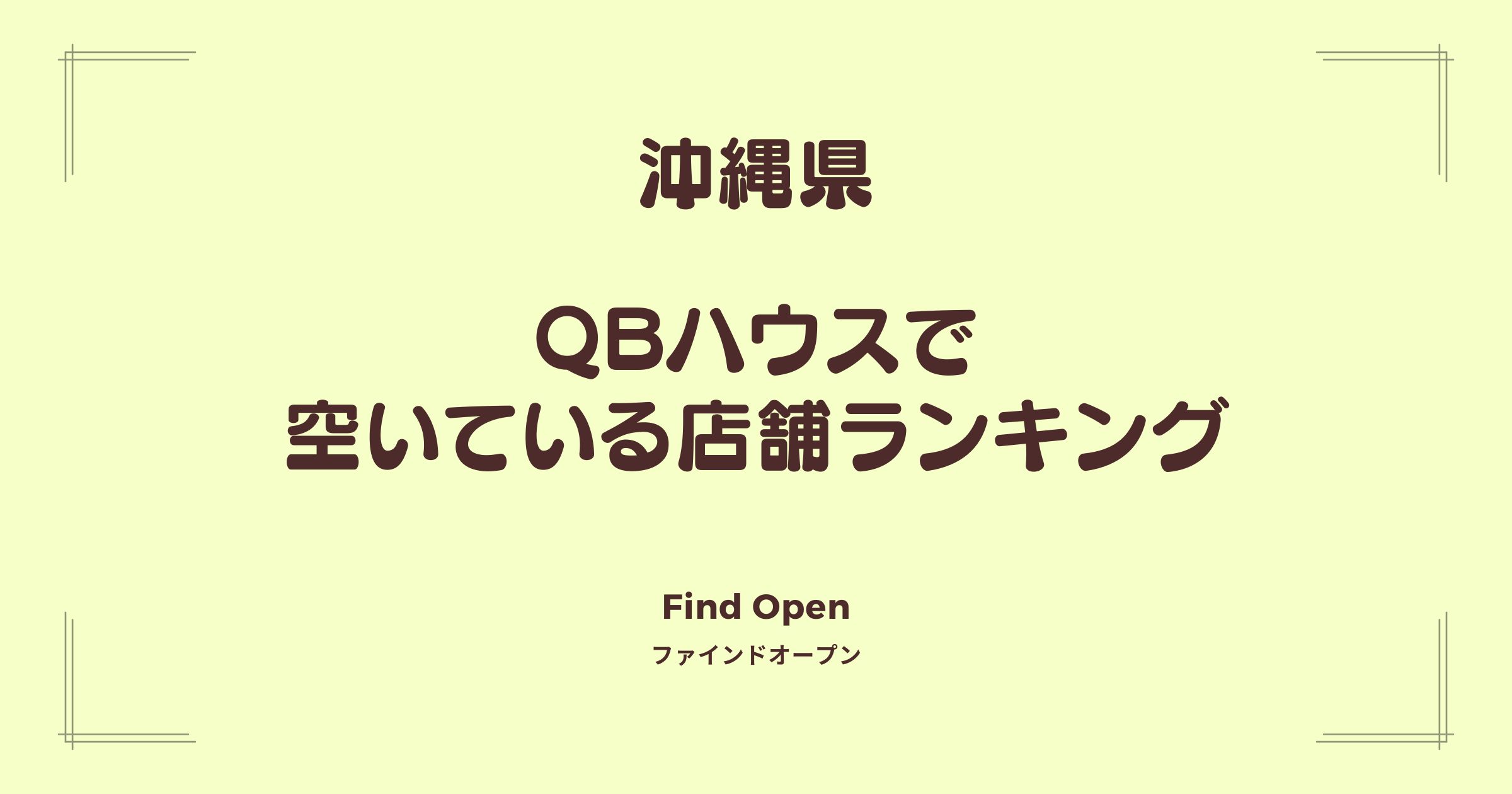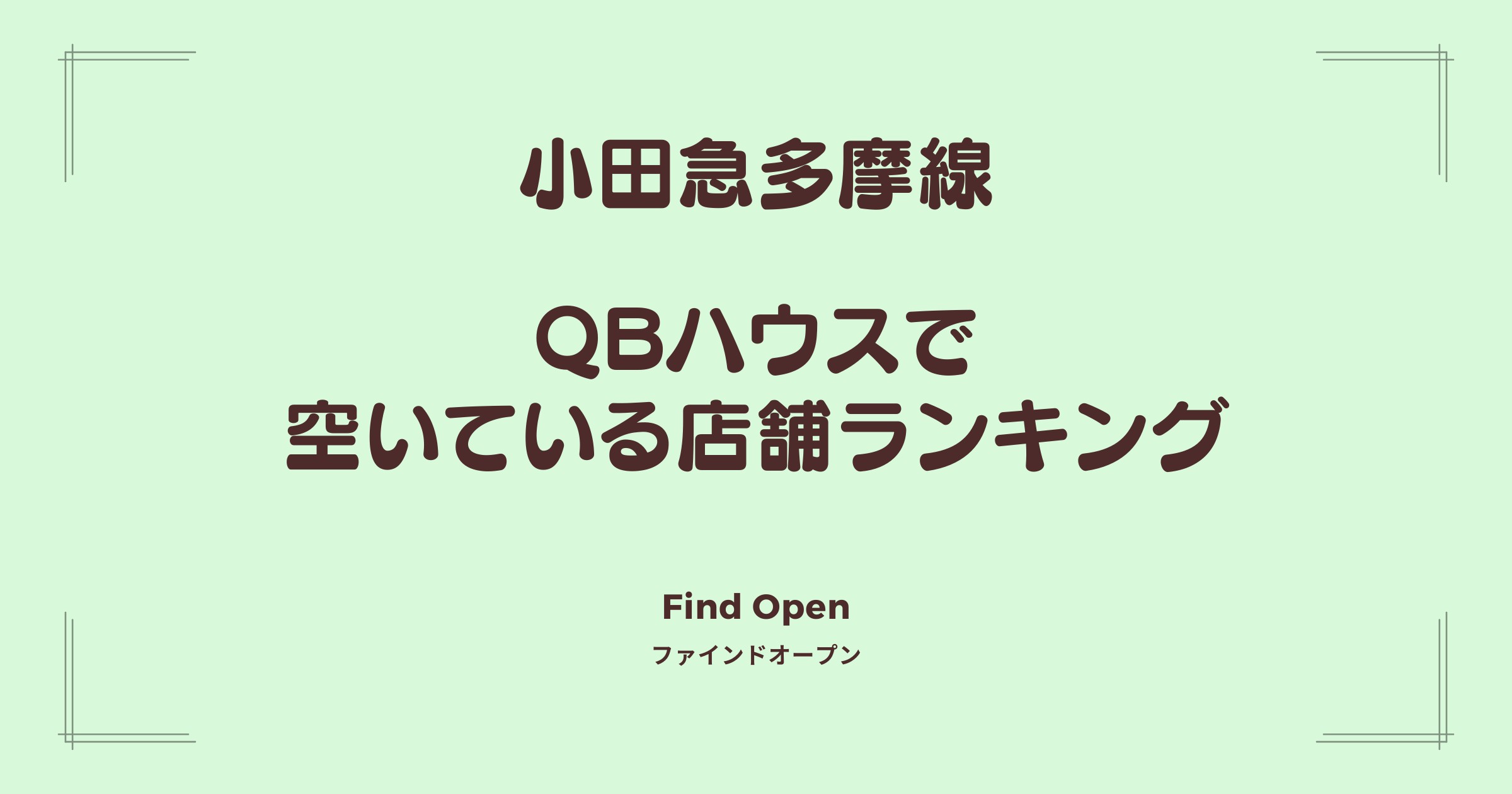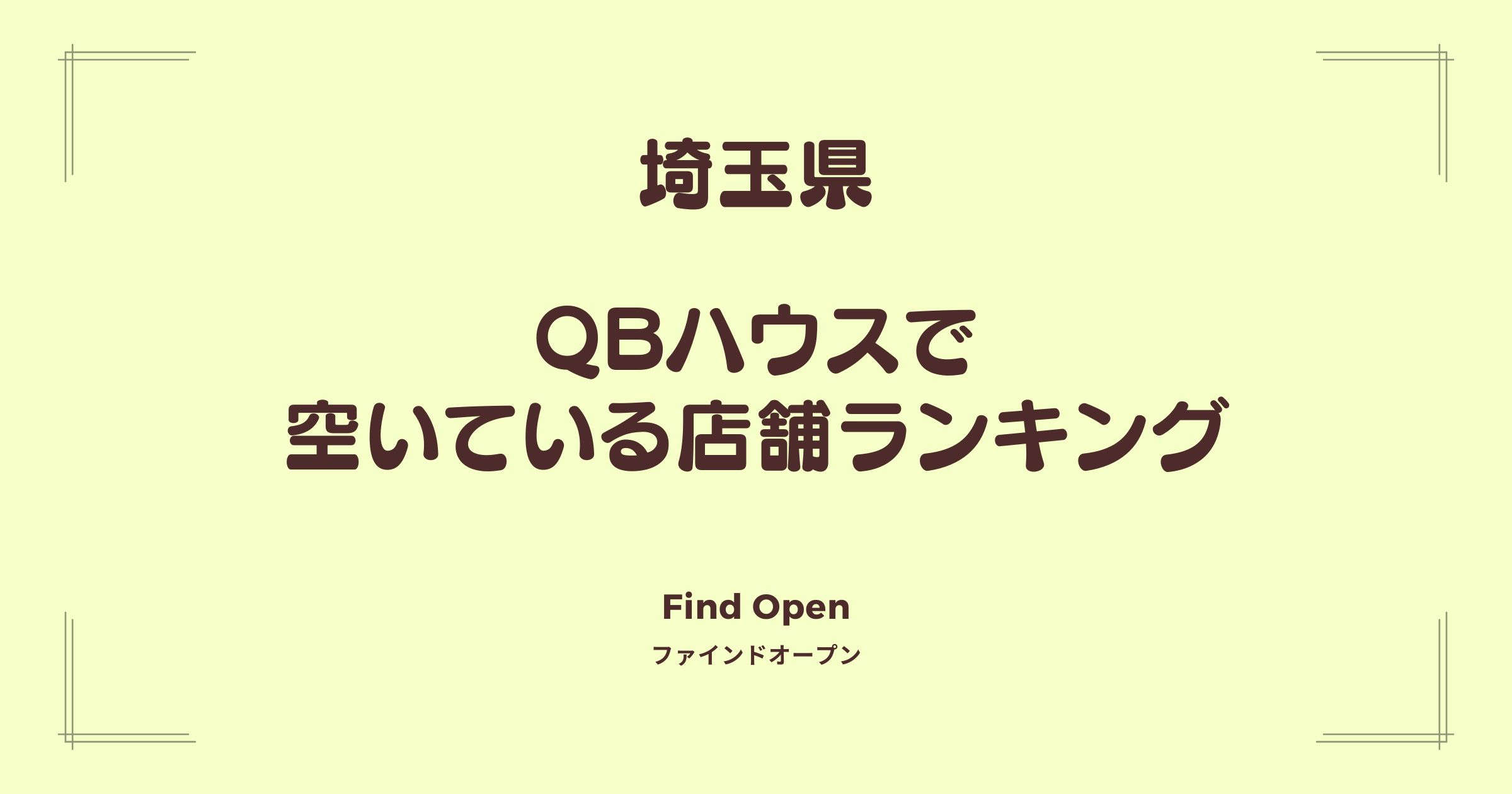目次
店頭ランプの色表示と待ち人数表示の仕組み
ランプ色ごとの待ち時間目安
QBハウス各店の入口には、信号機のような3色ランプ(QBシグナル)が設置されています。
このランプは混雑状況に応じて青(または緑)・黄・赤に点灯し、おおよその待ち時間を示します。青色ランプは「待ち時間なし(すぐ案内可能)」、黄色ランプは「5〜10分程度の待ち時間」、赤色ランプは「15分以上の待ち時間」を意味しています。
例えば青ランプであれば入店後すぐにカットに取りかかれる状態、赤ランプなら最低でも15分以上の待ち時間が発生している状態という目安になります。
特に赤ランプは「15分以上待ち」を示すカテゴリのため、実際には16分程度でも1時間以上でもすべて赤で表示されます。
そのため赤が点灯している場合、具体的な待ち時間は店舗に入って確認しないと分からないほど幅がある点に留意が必要です。
自動制御の仕組みと待ち人数カウント技術
店頭ランプの色はスタッフが手動で切り替えているのではなく、自動制御システムによって待ち人数に連動しています。
QBハウスでは来店時に券売機でカット受付券(チケット)を発券し、順番待ちの仕組みに入ります。
スタイリストが施術を開始する際にこのチケットに印字されたバーコードをスキャンすると、発券済みチケット総数からスキャン済み(対応済み)チケット数を引くことで現在何人の客が待っているかをシステムが把握します。
この待ち人数データに応じて店頭ランプが自動的に青・黄・赤のいずれかに点灯し、店外からでも一目で現在の待ち時間目安が分かるようになっています。
つまり使用中のカットブース数と未対応の発券枚数を元にしたリアルタイム連動で混雑度を表示しており、スタッフに声をかけなくても外から混雑具合を判断できるしくみです。
このようにデジタル技術を活用したQBハウス独自のランプ表示システムが、予約不要でも待ち時間を可視化するサービスを支えています。
リアルタイム混雑状況把握のニーズ
来店前に混雑を確認したい理由と利便性向上
待たずに素早くカットを終えたいというQBハウス利用者にとって、来店前に混雑状況を把握できることは大きなメリットです。
創業者の小西氏も「待ち時間が外から見えれば面倒な予約をしなくていい」と発想し、店頭ランプによる待ち時間表示を思いついた経緯があります。
このように予約なしで好きなときに行ける業態でも、事前に混雑を知っておけば時間ロスを減らせるため、リアルタイム混雑情報を求めるニーズは高いといえます。
実際、QBハウス社内でも「どこにいても待ち時間が見えたらもっと便利」との声が上がり、システムのアップデートによって現在は公式HP上で各店舗の待ち人数が確認可能となりました。
これにより店舗まで行かなくても自宅や移動中に混雑度を把握でき、待ち時間の少ない時間帯や空いている別店舗を選ぶことができます。
しかし、リアルタイム更新性については課題も指摘されています。
例えばある利用者はスマホで公式サイトの混雑情報を確認し「待ち人数0人」を見てから数分後に来店したところ、店頭ランプが赤に変わっており驚いたといいます(到着時に別の客が新たに来店したためと推測されます)。
この利用者がスマホ画面を再度更新しても0人のままだったことから、数分程度のタイムラグが生じうる点に不満の声が上がりました。
つまり現状の混雑表示は完全なリアルタイムではなく、一定間隔で更新されている可能性があります。
それでも、概ねの混雑傾向を事前に把握できるだけでも「行ってみたら混んでいた」という事態を避けやすくなり、時間の有効活用や心理的な安心感につながっています。
待ち時間を最小化してQBハウスの「省時間」メリットを最大限享受する工夫として、多くの利用者が事前の混雑チェックを活用しているのが現状です。
ランプ表示に対するユーザーの声
「ランプの点灯意味がわかりにくい」と感じるケース
店頭ランプは便利な目安である一方、実際の待ち時間とのズレや意味の伝わりにくさに戸惑う利用者の声も見られます。
例えば、「青(緑)ランプだったので待たずにカットしてもらえると思って入店したのに、実際は待ち時間があった」という声や、「赤ランプだったのに30分近く待たされた」という不満、「黄色ランプなので5〜10分待つ覚悟をしたら、数分で案内され拍子抜けした」といった体験談が報告されています。
これらはランプ表示があくまでおおよその目安であり、直前の状況変化や個別の要因で実際の待ち時間が前後しうることを物語っています。
特に赤ランプについて「15分程度の待ち時間だと思っていたら大間違い」との指摘もあり、極端な場合1時間待ちでも表示はずっと赤のままになるため、点灯色だけでは正確な待ち時間を読み取れない場合があると解説されています。
実際、QBハウス公式も「ランプ表示が正確な時もあるが誤差が生じる場合もある」と案内しており、ランプの情報は参考程度であることを認識する必要があります。
一方で、「店頭のランプ色で混雑具合が一目でわかるのはありがたい」といった肯定的な意見もあります。
価格口コミサイトなどでも「店の前にランプがあるおかげで、混んでいるかすぐ分かる」という声が見られ、従来の理美容店にはないQBハウスの利便性の特徴として評価されています。
。
総じて、ユーザーからは「便利だが完璧ではない」という反応が多く、待ち時間表示のわかりやすさ・正確さ向上に期待する声も上がっています。
スマホ連携サイネージの事例(他業種)
QBハウスのように混雑状況を可視化して顧客利便性を高める試みは、他の業種でも広く行われています。
スマートフォンと連動したデジタルサイネージ活用事例をいくつか紹介します:
テーマパーク(遊園地)
:東京ディズニーリゾートなど大規模テーマパークでは、公式スマホアプリ上で各アトラクションの待ち時間をリアルタイム表示しています。
パーク内の地図に現在の待ち時間が表示されるため、ゲストは移動中でも待ち時間を把握し、効率的に回る計画を立てることができます。
このようなアプリ連携により、「並んでみたら想像以上に待った」というストレスを減らし、顧客満足度向上に寄与しています。
飲食チェーン
:ファミリーレストランや人気ラーメン店などでは、スマホで順番待ちができるリモート受付システムを導入する例が増えています。
例えばEPARK等のサービスを使い、来店前にスマホから受付番号を取得しておけば、自分の順番が近づくまで店舗外で待機できる仕組みです。
店舗には順番待ち状況を表示するデジタル掲示が設置され、利用者はスマホ画面でも現在の待ち組人数や推定待ち時間を確認できます。
これにより長い行列にその場で並ぶ必要がなくなり、待ち時間を他の時間に有効活用できるようになっています。
駅・商業施設
:トイレやフードコートなど公共性の高い設備でも混雑可視化の取り組みがあります。
例えばJR博多駅ではトイレ個室の空き状況を検知するIoTセンサーを導入し、トイレ前のサイネージ画面および利用者のスマホからリアルタイムで空き個室数を確認できるサービスを開始しました。
これにより利用者は遠目にもトイレの混雑度がひと目で分かり、混雑時には他の階のトイレに回るなどの判断が容易になります。
商業施設全体でも、各店舗やフロアの混雑度を○△×などの記号や色分けで表示し、QRコード経由でスマホから詳細情報を見られる仕組みを提供する例もあります。
こうした館内混雑ナビはコロナ禍を経て需要が高まり、密集回避や回遊促進に役立っています。
イベント会場・スタジアム
:KDDIでは大型スタジアムでの混雑状況可視化に関する実証実験を行っています。
AI搭載カメラやLiDARで来場者数や流れを計測し、そのデータをクラウド上で解析することで、場内の混雑度マップを作成している事例です。
解析結果は会場内のデジタルサイネージ画面にリアルタイム表示されるほか、観客各自のスマホからも混雑マップページを確認できるようになっています。
このシステムにより観客は空いている売店やトイレの場所をひと目で把握でき、運営側も人の流れを見ながら誘導やスタッフ配置を調整できる利点があります。
2024年の本格導入を目指して検証が進められており、大規模イベントでの混雑緩和ソリューションとして注目されています。
ランプシステムの改良予定と導入効果
システム改良の最新動向
QBハウスでは店頭ランプ導入後も、更なる利便性向上のためシステム改良を続けています。
前述の通り、当初は店舗まで行かないとランプを確認できない状況でしたが、現在は公式ウェブサイト上で各店舗の待ち人数を表示するようアップデートされています。
このHP上の混雑情報はスマホから手軽に閲覧可能で、利用者は自宅や移動中に最寄り店の待ち時間をチェックしてから出向けるようになりました。
また2020年には新業態「QBハウス プレミアム」が開始され、こちらではスマホアプリ連携による予約・順番受付システムが導入されています。
通常のQBハウス店舗が店頭3色ランプによる当日先着順制であるのに対し、プレミアム店舗では専用アプリ「QBパスポート」から事前に日時予約が可能で、受付後は自分の順番進行もスマホで確認できます。
さらに順番が近づくとメール通知が届き、店内で長時間待つ必要がない仕組みも取り入れられています。
このようにスマホ連動機能の強化や予約オプションの導入など、QBハウスは顧客のニーズに合わせて混雑案内システムの改良を進めています。
現時点で通常業態のQBハウス全店に予約制を導入する予定は公表されていませんが、混雑情報のオンライン提供という点ではすでに全店舗で実現しており、今後もさらなる分かりやすさ向上や他チャネル連携が期待されます。
ランプ導入の効果とデータ活用
店頭ランプ「QBシグナル」の導入による効果としてまず挙げられるのは、顧客の行動選択支援と機会損失の削減です。
ポーター賞の受賞企業レポートでも、QBハウス各店舗が待ち時間を店外のランプで表示することでお客の判断を助け、さらにスマホを通じて近隣店の混み具合も分かるようにすることで機会損失を減らしていると評価されています。
実際、ある店舗が赤ランプ(混雑)だった場合でも、ユーザーはスマホで近隣店舗の空き状況を調べて緑ランプ(空いている)店舗に回るといった選択が可能です。
これにより「混んでいるから利用を諦める」客を他店へ誘導でき、結果として来客機会のロスを最小限に抑える効果が生まれています。
また、店頭ランプのデータは社内の運営指標としても活用されています。
QBハウスでは各店のランプ点灯状況、つまり混雑(赤・黄)比率を重要KPIの一つとしてモニタリングしており、2023年にはコロナ禍前を上回る水準で赤黄ランプ比率が推移したことが報告されています。
これは需要回復によって多くの店舗で混雑状態が増えたことを示し、経営側では混雑率のデータを基に人員配置や新店計画の判断を行っています。
さらに蓄積した膨大な混雑データの分析により、時間帯ごとの混雑予測もかなり正確に行えるようになっています。
QBハウスではこの予測情報を活かし、近隣店舗間でスタイリストを時間単位で融通して配置するなど、需要の山谷に合わせた機動的なオペレーションを実現しています。
例えば昼休み時間帯にある店舗が混み合うと予測される場合、事前に別店舗から応援スタッフを派遣し、待ち時間が極端に延びないよう調整するといった取り組みです。
店頭ランプは単なる顧客向けサービスに留まらず、社内のデータ主導型経営を支える装置にもなっていると言えるでしょう。
総合すると、QBハウスのランプ表示システムは予約不要でも待ち時間を「見える化」する革新的な仕組みとして顧客の時間節約ニーズに応え、利便性を高めてきました。
その一方で「色だけでは細かな待ち時間までは分からない」という課題もあり、同社はウェブやアプリとの連携強化など改善を進めています。
今後も顧客の声を反映しながら、このランプシステムがより分かりやすく正確で役立つ情報提供ツールへと進化していくことが期待されます。